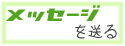|
みてみん |
| 登録 タグ |
*シモウサへようこそ!
*下総国
*令制国
*小説家になろう
*アルファポリス
→編集を行うにはログインしてください |