
|
みてみん |
|
投稿日時 2025-05-15 08:32:54 投稿者 
一ノ宮ガユウ このユーザのマイページへ お気に入りユーザ登録 |
投稿者コメント | |
|
コラム(13) 富士見町東部の変遷 ~ (15) 長島の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5607324 古代 加賀・越前の国界は織豊期に変動し、白山連峰の西麓・手取川最上流域の東谷・西谷は越前国に属するようになった。 室町期から戦国期にかけて、浄土真宗 (真宗) 本願寺派の門徒は組織を形成し、近畿・北陸・中部の各地で支配者に対して武力蜂起した (一向一揆)。特に加賀国では、長享2年(1488) 守護の富樫政親を倒して門徒が自ら国を経営する体制を確立し、内紛や変質を経験しながらも長く持ちこたえた。しかし天正年間(1573~1592) に入ると、織田信長の猛攻によって各地の一揆は壊滅し、主導する石山本願寺も籠城戦に追い込まれるなど周辺状況は悪化していった。天正3年(1575) には信長によって加賀の一揆も南部を制圧され、天正7年(1579) には柴田勝家・佐久間盛政 (勝家の甥) が越前から本格的に侵攻、次々に拠点を攻略していった。 7月には佐久間盛政・柴田勝政 (盛政の実弟、同じく勝家の甥だがその養子となった) が越前から加賀へ谷峠を越えて侵入し、手取川最上流域の 3つの谷筋のうちの東谷・西谷を支配する加藤藤兵衛は屈服した。盛政はこれを受け容れ、加藤に東谷・西谷を安堵することで引き続き支配することを許し、このとき東谷・西谷の村々 (近世 須納谷・白山新保・島・杖・丸山・小原・牛首・下田原・鴇ケ谷・深瀬・釜谷・五味島・二口・女原・瀬戸・風嵐の 16村) は柴田勝家の所領 (越前領) に組み入れられた。一方、残る尾添谷 (近世 尾添・荒谷の 2村) は、東谷・尾添谷が合流する付近の村々 (近世 吉野・佐良・瀬波・市原・木滑・中宮の 6村) とともに抵抗を続けたが、天正10年(1582) に殲滅された。 この一連の出来事について直接の史料は残っておらず、すべて江戸期からさかのぼって記述された文書による。しかし、対立関係にあった牛首村と尾添村の文書に矛盾はなく、牛首村については「白山麓拾八ケ村留帳」のほか、享保16年(1731) の「白山麓九カ村検地御尋に付口上書」などに、尾添村については寛文6年(1666) の白山一巻や元禄10年(1697) の「白山争論に付尾添村訴状控」などにそれぞれ記述されている。また、吉野村の貞享3年(1686)「石川郡吉野村平三郎由緒」 や、白山比咩神社の元禄元年(1688)「白山年代記幷由緒」 にも同様の記述がある。ただし、どれも東谷・西谷の 16村が柴田勝家の所領 (越前領) となったことと、越前国の一部になったこととを区別していない。 一方、越登賀三州志と白山下御公領等之覚書はともに豊臣政権下、秀吉が丹羽長秀に越前国を与えた時に 16村を含む検地が行われ、このときに国郡が確定したとしており、厳密な時期としてはこちらが正しいと考えられる。丹羽長秀の越前国における検地は天正12年(1584) である 。なお、両者とも 16村の自認が天正7年(1579) であることは否定していない。 |
||
|
最大化 | アクセス解析 | ユーザ情報 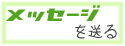 |
▽この画像のトラックバックURL▽(トラックバックについて) |
|