
|
みてみん |
|
投稿日時 2025-06-06 12:25:45 投稿者 
一ノ宮ガユウ このユーザのマイページへ お気に入りユーザ登録 |
投稿者コメント | |
|
コラム (21) 小豆島の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5439781 古代 備前・讃岐の国界は戦国期に曖昧化し、近世以降、備前国にあった小豆島・直島は讃岐国に属するようになった。 小豆島は日本書紀に「阿豆枳辞摩」としてあらわれ、これにより本来は「あづきしま (あずきしま)」だったことがわかる。その後「小豆島」と書かれたものが音読みされて現在の読みになったらしい。永仁5年(1297) 御所大番役定書案に「せうつしまの庄」とあり、すでに「ショウツシマ」と読まれている。奈良期の平城宮木簡に「備前国児島郡小豆郷」、続日本紀の延暦3年(784) の記事にも「備前國兒島郡小豆嶋」とあるように小豆島は備前国 児島郡に属した。 小豆島には平安末期までに小豆島庄・肥土庄が成立し、基本的に前者は石清水八幡宮領、後者は皇室関係の所領として継承されていく。小豆島庄がはじめて史料にあらわれるのは、前述の永仁5年(1297) 御所大番役定書案に「せうつしまの庄」とあるものだが、先行する建長2年(1250) の九条道家初度惣処分状に荘園 (庄・御厨) と並んで「備後国小豆嶋」がある。肥土庄は治承2年(1178) の後白河院庁下文にはじめてあらわれ「備前國肥土庄」とある。このほか、建治元年(1275) の長勝寺鐘銘文に「小豆島西方池田御庄」とある池田庄、応永4年(1397) 草加部八幡宮鰐口銘や応永14年(1407) 八幡宮鰐口銘に「小豆島草賀部庄」とある草加部 (草賀部) 庄、寸簸之塵 所収の永禄9年(1566) 備前国郡郷庄帖に「尾美庄・草部庄・池田庄・肥土庄」(中黒は筆者が補う) とある尾美庄が知られる。基本的に小豆島庄が分割されたか、内訳 (広域地名) として池田庄・草加部 (草賀部) 庄・尾美庄が存在したと考えられるが、詳細はわからない。 南北朝期に入ると、延元4年(1339) までに備前国 児島郡の飽浦を本拠とした佐々木 (飽浦) 信胤が占拠し、この段階で各荘園は実態を失ったとみられる。その後、貞和3年(1347) 細川師氏に攻め込まれると信胤はその配下となり、小豆島は細川顕氏を経て細川頼之の所領に組み込まれ、南北・室町期を通じて讃岐国守護・管領細川氏の勢力下に置かれるところとなった。 この間、延元2年(1337) 後醍醐天皇倫旨に「備前國小豆島」、応永2年(1395) 応永備前神名帳に「備前国小豆島郡」、応永24年(1417) 淵崎八幡神社旧蔵青銅製鰐口銘・応永31年(1424) 雲故庵大般若波経奥書に「備前国小豆島肥土庄」「備前国小豆島北浦小海郷」、文明15年(1483) 福寿借銭状に「備前國小豆島」とあるなど、引き続き備前国の一部として認識されている。 |
||
|
最大化 | アクセス解析 | ユーザ情報 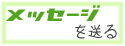 |
▽この画像のトラックバックURL▽(トラックバックについて) |
|