
|
みてみん |
|
投稿日時 2025-06-06 12:27:04 投稿者 
一ノ宮ガユウ このユーザのマイページへ お気に入りユーザ登録 |
投稿者コメント | |
|
コラム (21) 小豆島の変遷 https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/5439781 一方、応永19年(1412) と推定される安富宝城書状では、東寺から備前国分の棟別銭を求められたことに関連して、「この島は備前の内であるとも、内ではないとも、いまだ決まっていない島である」 という見解が示され、蔭涼軒日録の明応2年(1493) 6月18日の記事でも「讃岐国は 13郡からなり、6郡は香川氏の支配、7郡は安富氏の支配である。小豆島も安富氏の支配である」 と、讃岐国とは別に小豆島支配の説明がある。安富氏・香川氏はともに守護・細川氏の代官 (守護代) である。これらによれば小豆島の国郡は曖昧化しており、また (備前国でも讃岐国でもなく) 小豆島は小豆島である、という傾向がみられる。ただし明王寺釈迦堂には「大永八年五月五日 宥泉之書」と刻まれた瓦と「讃州小豆島池田之住人 宥泉」と刻まれた瓦があり 、大永8年(1528) の時点で讃岐国と自認する住人がいたことがわかる。 これは戦国・織豊期を経て江戸期に入ってからも同じで、慶長10年(1605) の徳川政権 (江戸幕府) による池田村の検地帳表紙には単に「小豆島之内池田村」とあって 国郡の記載はない。慶安元年(1648) 坂手村の検地帳でも「小豆島之内草加部村」(中略)「坂手村分」、延宝7年(1679) 福田村・吉田村の検地帳 でも「小豆島福田吉田村」 とだけある。 一方、慶長の備前国絵図や、寛永年間(1624-1644) の備前国九郡絵図、寛永10年国絵図の縮写図とされる「日本六十余州国々切絵図」の備前国や、この秋田県公文書館所蔵のものに混入する寛永15年国絵図の備前国のどれにも小豆島は含まれない。天保の備前国絵図・郷帳でも同様である。 対する讃岐国については史料が限られるが、日本六十余州国々切絵図の讃岐国に小豆島が描かれ、この原本と考えられる「寛永十年讃岐国絵図」でも同様と推定される。 天保の讃岐国絵図・郷帳では小豆島はどの郡にも含まれず、同格の枠組みで別に「小豆島」とあって各村が含まれている。 これらからいえば江戸初期には讃岐国として把握されていたと考えられるが、郡の扱いはきわめて曖昧なまま扱われたといえる。 |
||
|
最大化 | アクセス解析 | ユーザ情報 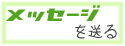 |
▽この画像のトラックバックURL▽(トラックバックについて) |
|