
|
みてみん |
|
投稿日時 2025-07-21 16:02:32 投稿者 
一ノ宮ガユウ このユーザのマイページへ お気に入りユーザ登録 |
投稿者コメント | |
|
コラム (4) 近世の下総国 (c) https://www.alphapolis.co.jp/novel/214885297/89423550/episode/9812742 この付近では、古くから結城氏が下総を、小山氏が下野を勢力下に置いていた。この構図は中世を通して変わらなかったが、周辺諸氏との争いは絶えず、また南北朝期に小山義政(※ふりがな※:よしまさ)の乱 (天授6年/康暦2年~弘和2年/永徳2年,1380~1382)、室町期に結城合戦 (永享12年~嘉吉元年,1440~1441) が展開されるなど、動乱の舞台にもなった。戦国期には、はじめ古河公方と関東管領・上杉氏の対立、のち後北条氏と上杉氏をはじめとする戦国大名の争いに巻き込まれ、小山氏の祇園城 (小山城、現在の小山市 城山公園) は天正3年(1575) 北条氏照に奪われた。その後、祇園城には天正10年(1582) 小山秀綱が形式的に復帰するものの、天正18年(1590) に結城晴朝によって攻略された。 小山秀綱と結城晴朝は兄弟であり、父は小山高朝、祖父は結城政朝という関係にある。結城晴朝の祇園城攻略は、すでに豊臣秀吉が小田原城を包囲する状況にあって、豊臣陣営についた立場としてやむを得なかったのだろう。小山氏の旧臣が内応したともいわれる。いずれにせよ、これによって小山氏の旧領 (小山領) のほとんどは結城氏の所領に組み込まれることになった。 慶長6年(1601) 関ケ原の戦い後、晴朝から家督を継いでいた結城秀康は論功行賞により越前北庄 (現在の福井) へ加増・転封された。結城氏の旧領 (結城領) は山川領とともに一時的に幕府直轄地となって代官・伊奈忠次の支配下に入ったとみられ、小山領についても同様と考えられている。伊奈忠次が慶長7年(1602) 上山川・大木・結城寺の各村で検地を行った記録が残っており、次の安藤重信・壬生藩が慶長17年(1612) 上山川・大木村で、小山に入った本多正純が慶長18年(1613) 神鳥谷・黒本・大行寺などの各村で、古河に入った奥平忠昌が元和7年(1621) 乙女村・横倉村などで、同じく永井直勝が元和9年(1623) 野田・横倉・土塔・黒本・大行寺などの各村で、出羽久保田藩 (秋田藩) が寛永5年(1628) 藩領としては飛地の上茅橋・飯田・山田の各村で それぞれ検地を行った記録が残っている。高椅地域については寛永14年(1637) 高橋村・中島村で、同15年(1638) 延島村で行われた記録が最初で、中島村については検地帳も現存し、その表紙には「下野国結城領中嶋村」とある。したがって、高椅地域はこのときまでに下総国 結城郡から下野国 都賀郡に移されたといえる。 慶長6年(1601) ~寛永14年(1637) の具体的にどの時期なのかは記録が残っていないためわからないが、同時期の寛永14年(1637) に結城本郷・武井村 (結城郡) でも検地が行われたことや、寺社の朱印状・在地での認識 (どちらも後述) を踏まえると、それ以前ではなく寛永14年(1637) に周辺一帯の国郡が再編成され、この過程で高椅地域は下野国 都賀郡に移されたとするのが妥当といえる。なお正保の下野国郷帳 (東野地誌)、およびこれに対応する中川忠英旧蔵 下野国絵図では、高椅地域の村々は下野国に含まれている。 |
||
|
最大化 | アクセス解析 | ユーザ情報 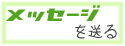 |
▽この画像のトラックバックURL▽(トラックバックについて) |
|